何度も歩いた事がある辺りですが、ところどころに懐かしさを感じる風情があります。
東京メトロ日比谷線の三ノ輪で下車し、JR常磐線のガードが見える方向に少し進むと、三ノ輪橋
跡の道標があります。

明治の終わり頃、ここには音無川と呼ばれた川がありました、その源は小平市の石神井川で、
北区の王子まで流れ、そこから音無川となってこの三ノ輪橋の下を流れ隅田川へと流れていました、
今ではもう暗渠となっています。
その標識から裏通りへと入ると浄閑寺があります。
以前、少しだけ紹介したことがありますが、新吉原の遊女が死後、投げ込まれたお寺です。
浄閑寺には、彼女達を慰霊した「新吉原総霊塔」があります、安政2年の大地震による、
新吉原の遊女の死者500人余り、以降2万人あまりの遊女が祀られています。

台座には花又花酔の句が埋め込まれています。

「生まれては苦界死しては浄閑寺」とあります、
彼は昭和30年代に亡くなられたそうですが、吉川英治と交際があったようです。
この川柳以外には目立った川柳はないようですが、花街にはよく出入りして
いたとの事でした、それにしても実感がこもった川柳です。
総霊塔と向い合って、永井荷風の「震災」の詩碑があります、長文ですが
最初の書き出しは
「今の世のわかき人々われにな問ひそ今の世と
また来る時代の藝術を。われは明治の兒ならずや。
その文化歴史となりて葬られし時わが青春の夢もまた消えにけり。〜」
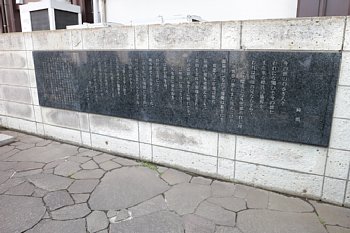
震災で江戸から明治へと変遷し古き時代が消え去っていくのをノスタルジック
に表現しています、花又花酔と同様に廓に通い、ここ浄閑寺をたびたび訪れ、
死後は、この寺での埋葬を願っていましたが、それも叶わず雑司ヶ谷墓地
に埋葬されましたが、その気持を汲んだ人により詩碑ができました。

ここ、浄閑寺では他にも、いわくつきの慰霊碑やら、記念碑があります、
これは遊女若紫の墓、明治31年、16歳のとき、新吉原の遊郭角海老に
身売りされ、5年の年季明けの5日前、8月24日に狂人に殺されたという、
年季明けには将来を約束した人との生活が待っていました、。
22歳の若さでした。
この墓は、あわれに思った遊郭の主人が建てたといいます。

この涸れ井戸は本庄兄弟の首洗い井戸と言われています、鳥取藩士の
平井正右衛門は本庄助太夫とささいな犬のことで言い争いをし、息子の
長男で平井権八は本庄助太夫を殺害し江戸へ逃れました。
1672年18歳の時でした。
殺害された父の仇を追いその遺児、助七、助八は江戸へと上り、敵を探し
ていましたが、それが権八の知るところとなり、兄の助七は吉原田圃で殺され、
兄の首を井戸で洗っていたところを再び、権八に襲われ殺害されてしまいます。
表札には万治3年とありますが万治3年は1660年で時代が合わないのは
どちらかが違っているのでしょう。
平井権八は歌舞伎にも白井権八として登場しています。
芝居では彼は、吉原の遊女小紫に通い詰め、やがて、金銭を使い果たし、殺人、
辻斬を重ね、目黒にある東昌寺に匿われましたが、やがて改心し、
虚無僧となって郷里へと両親に逢いにいきましたが、すでに他界しており、
江戸へ戻った権八は自首をして鈴ヶ森で磔となりました。
権八の遺体は東昌寺の住職が引取り、その報を聞いた、小紫は権八の墓前
で後追い心中をしまいた、のちの世にこの東昌寺にその霊を弔い比翼塚が
東昌寺にたてられました。

この写真は浄閑寺の門前近くにある、新比翼塚です。
明治18年、新吉原の品川楼で、遊女、盛紫と当時の内務省の警部補、谷豊栄
が心中し話題となった事件がありました、それを弔った塚だそうです。
比翼塚というのは情死した男女を弔う塚の意味があるそうです。

そして、最後に門前にある浄閑寺の説明板の横にあるのが小夜衣供養地蔵尊です、
通りすがりの人が体の悪い部分を撫でると良くなるという言い伝えもあり、また、
遊女小夜衣の供養塔という言い伝えもあります、吉原の遊郭四つ目屋で家事が起き
店の主は犯人は小夜衣と訴え、彼女は火炙りにされましたが、その後も四つ目屋の
火災は続き、店は潰れたといわれその供養のために作られたという話です。
民間伝承のお話はどこにでもありますが、吉原近くの浄閑寺ならではの言い伝えでしょうか。
浄閑寺を後にして、せっかくなので、廓跡を通って一葉記念館方面を歩いてみることにしました。

ユニークな旅館がありました、名前は「行燈旅館」デザインはなんとも言えない現代風ですが
どことなく和風を感じさせます、あとで調べたら、外国からのバックパッカー向けの
宿だそうで、一泊食事なしで6,100円から宿泊でき、けっこう人気があるようです。

そこから、しばらく歩くと、こんな看板が....
あしたのジョーの原作者の梶原一騎がこの付近で生まれたことから街興しに
利用されているようです。

でも、場所がら、ドヤ街らしさも残っていて、こんな不気味な落書き(?)もあります、
まあ、人通りはかなり少ない商店街でした。

ここは東禅寺、この地蔵様は江戸六地蔵の一つ、銅造地蔵菩薩坐像です。
説明によれば、1710年、深川の地蔵坊正元が病気から治癒し、その感謝
のため建立を祈願して人々から浄財を集め江戸の六ヶ所に勧請したそうです。
今と違い、病気治癒の感謝の念というのは、薬も満足にない時代の人にとっては
とても強いものだったのでしょうね。

東禅寺から少しばかり離れた場所にあるのが春慶院です。
この墓は新吉原三浦屋の名妓、高尾太夫二代目のお墓です、俗に
萬治高尾、仙臺高尾などと呼ばれていました、説明板には二代目とありますが、
三浦屋傳説では、三代高尾、榊原所蔵本では初代高尾ともいわれているよう
です、まあ、何代目とかは....
ところで、仙臺という名がつくぐらいですから、仙台との関係では、こんな逸話
がありました。
第三代仙台藩主の松平陸奥守綱宗は遊郭通いのあげく、三浦屋の高尾太夫に
惚れ込んでしまいました、高尾太夫も、綱宗にたいしては、「君はいま駒形あたり
ほととぎす」という句を贈っていました、一時は身請けの話までいったそうですが、
高尾太夫はそれを固辞したため、川遊びに誘い、殺害したという話が残っています。
高尾太夫の没年は萬治二年十二月五日とありますが、十二月に川遊びは難しい
かもしれません。
事実はどうかとしても、その翌年の萬治三年八月二十五日に伊達綱宗はまだ21歳
で幕府により隠居を命ぜられ、家督をまだ二歳の亀千代に譲ることになりました。
その後、寛文十一年(1671年)3月に藩内の補佐役の奉行達で内紛が発生し
刃傷沙汰が発生してしまいました、この事件が俗にいう伊達騒動と云われています。
亀千代は幼かった事もあり、元服が認められ伊達綱村として親政がはじまりました。
しかしながら、綱村は藩政には貢献はしたものの藩の重職に側近を登用したことや、
藩の財政圧迫などで反発をうけ、事態がやがて幕府の耳に入る事となり
、元禄十六年(1703年)四十あまりで父の綱宗同様に隠居を命ぜられることになりました。

話が長くなりましたが、そこからしばらく歩くと昔の遊郭あたりにはこの辺りが
江戸の遊郭、吉原揚屋町だった事を標識が示しています。
その先は、一葉記念館ですが、その日は休館日で樋口一葉記念公園で休憩。
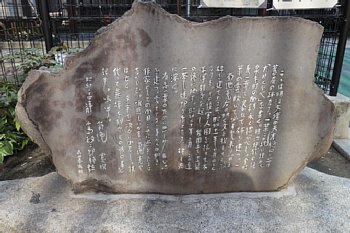
公園には一葉を偲んだ碑があります。
碑文には
「ここは明治文壇の天才樋口一葉旧居のあとなり。一葉この地に住みて
「たけくらべ」を書く。明治時代の竜泉寺町の面影永く偲ぶべし。
今町民一葉を慕ひて碑を建つ。一葉の霊欣びて必ずや来り留まらん。
菊池寛右の如く文を撰してここに碑を建てたるは、
昭和十一年七月のことなりき。
その後軍人国を誤りて太平洋戦争を起し、我国土を空襲の惨に晒す。
昭和 二十年三月この辺一帯焼野ケ原となり、碑も共に溶く。
有志一葉のために悲しみ再び碑を建つ。愛せらるる事かくの如き
、作家として の面目これに過ぎたるはなからむ。唯悲しいかな、
菊池寛今は亡く、文章を次ぐ に由なし。
僕代って蕪辞を列ね、その後の事を記す。嗚呼。
昭和二十四年三月 菊池 寛 撰
小島政二郎補並書 森田春鶴 刻
と刻まれています。
江戸から明治、大正へと時代は変わって、文明も進みましたが変わらぬ人の
思いがこの地域には残っていました。
<戻る>